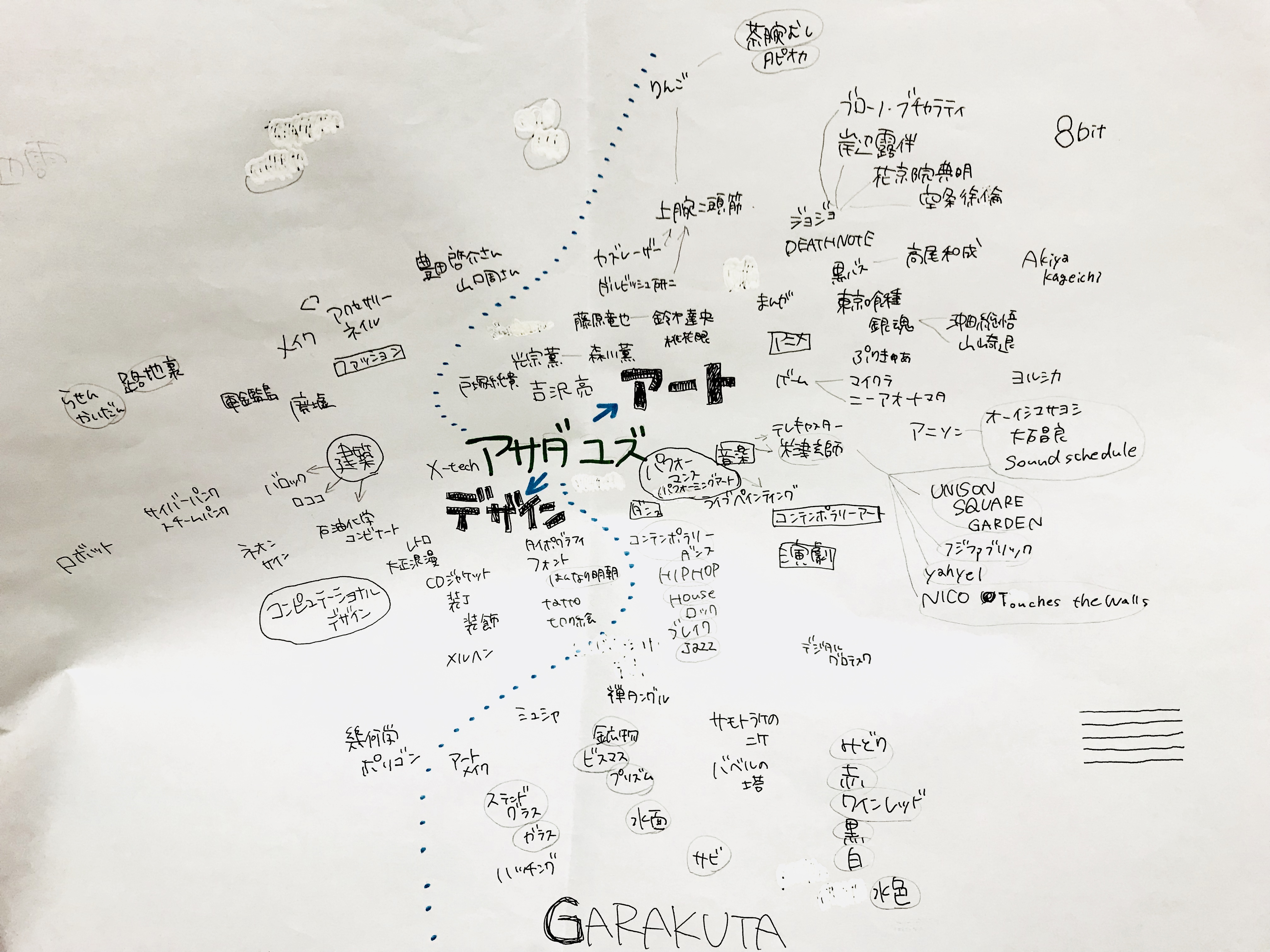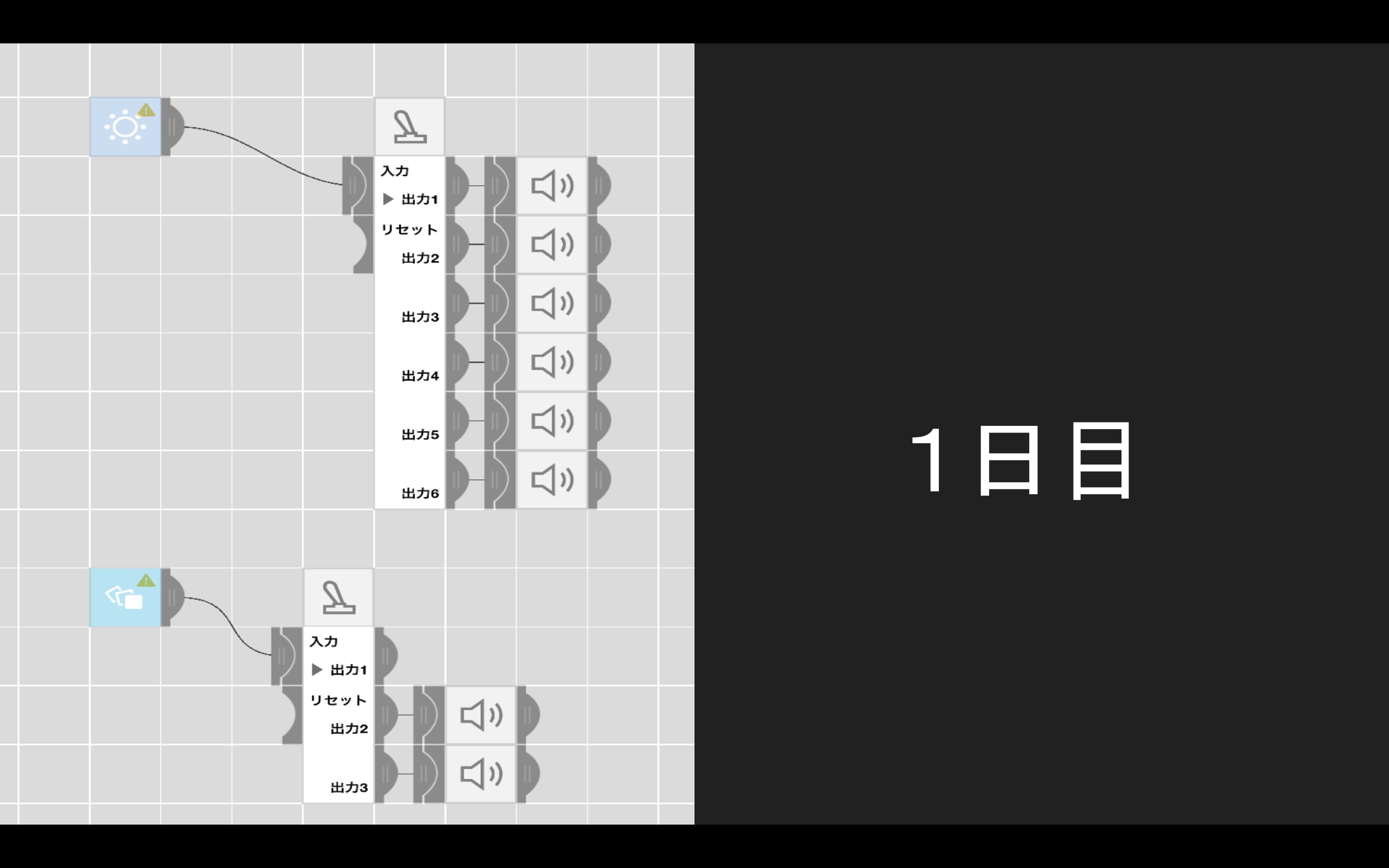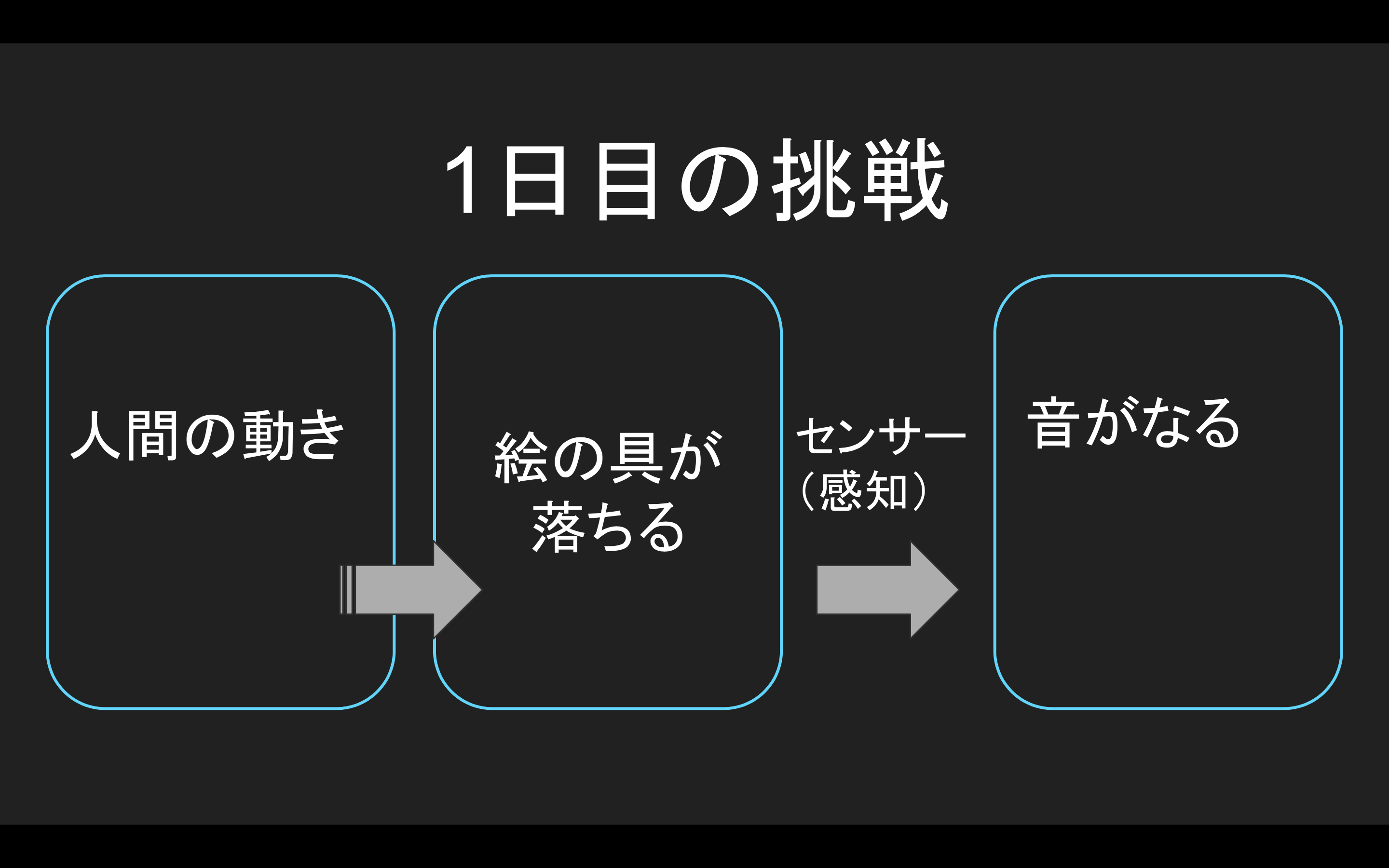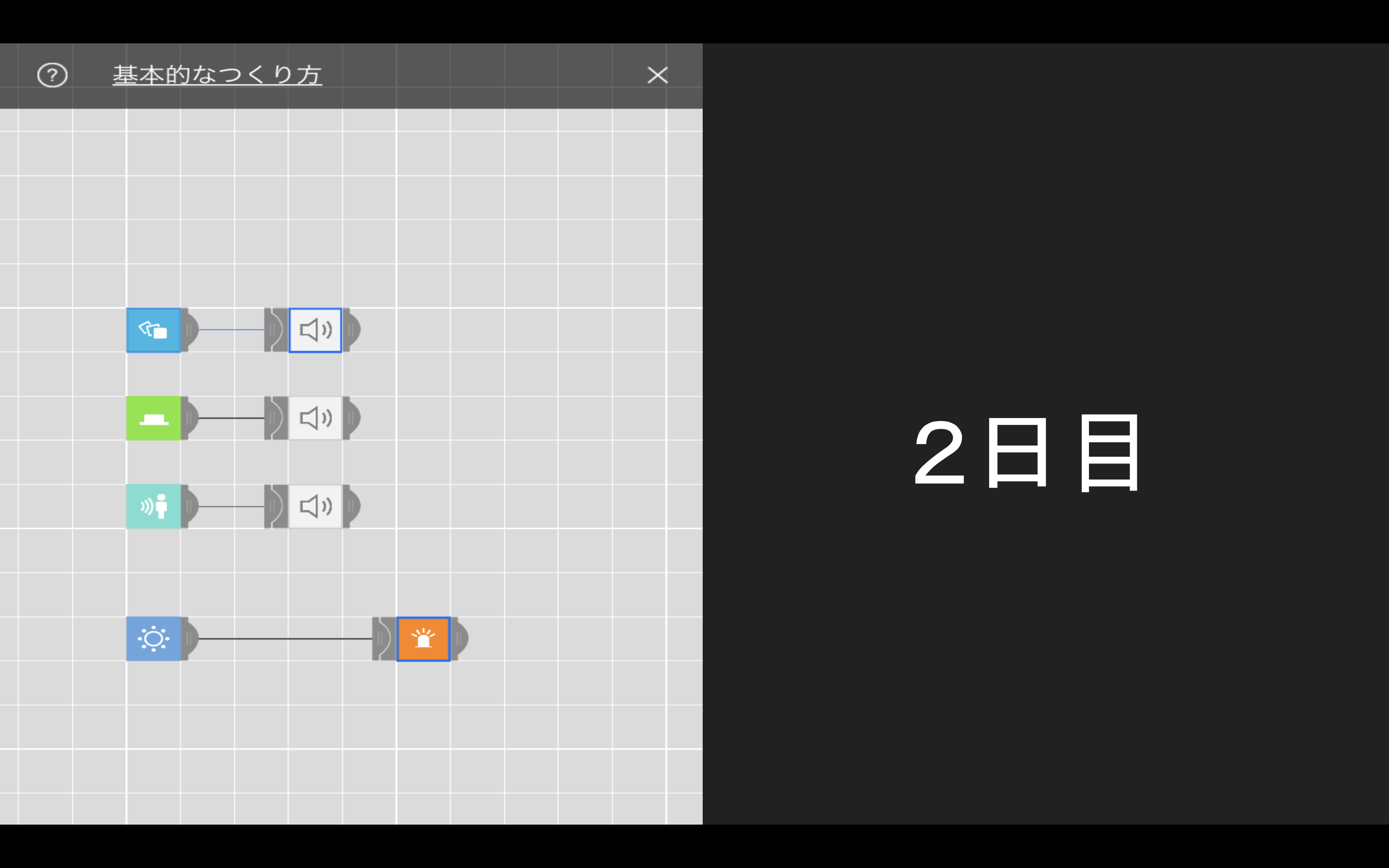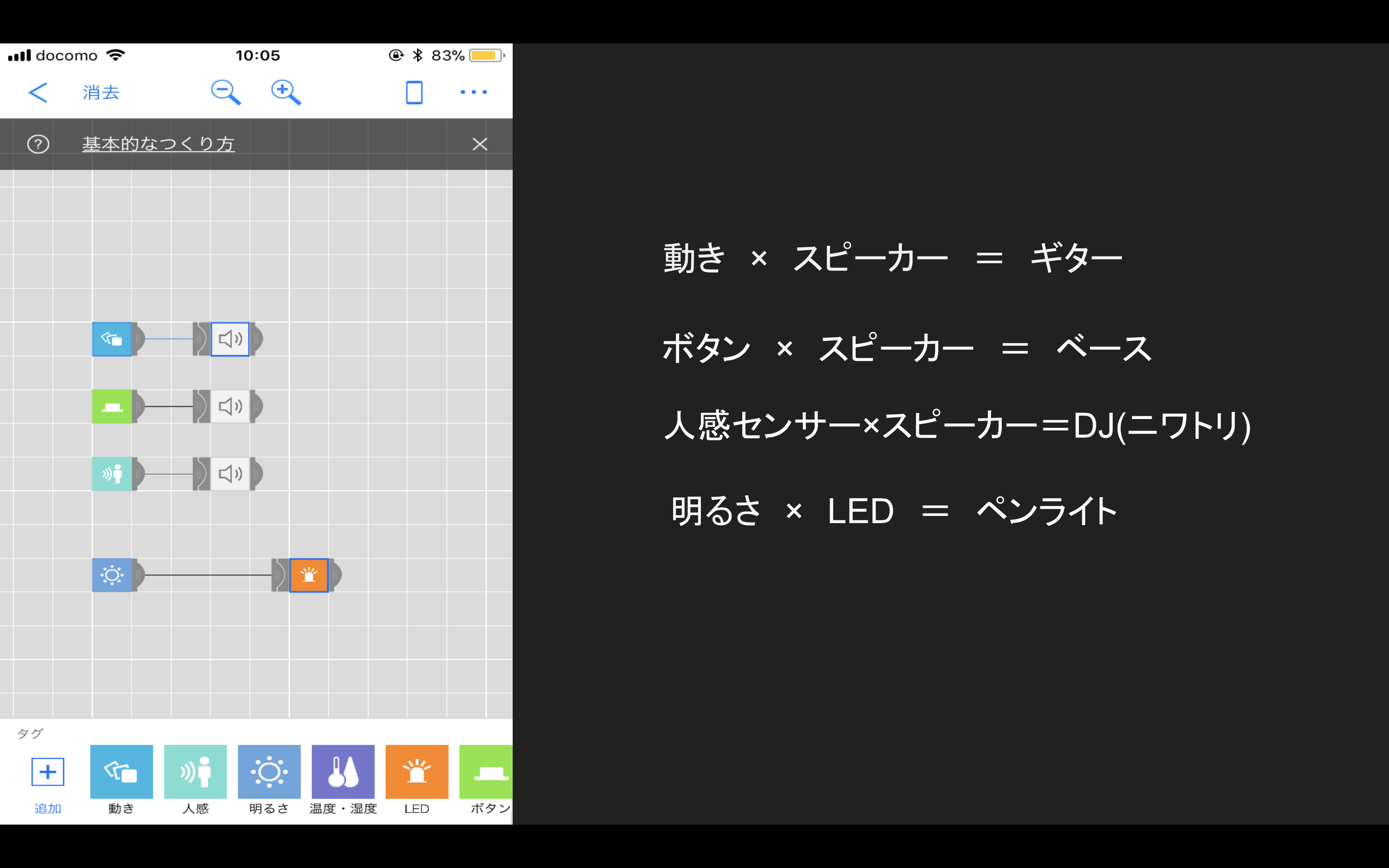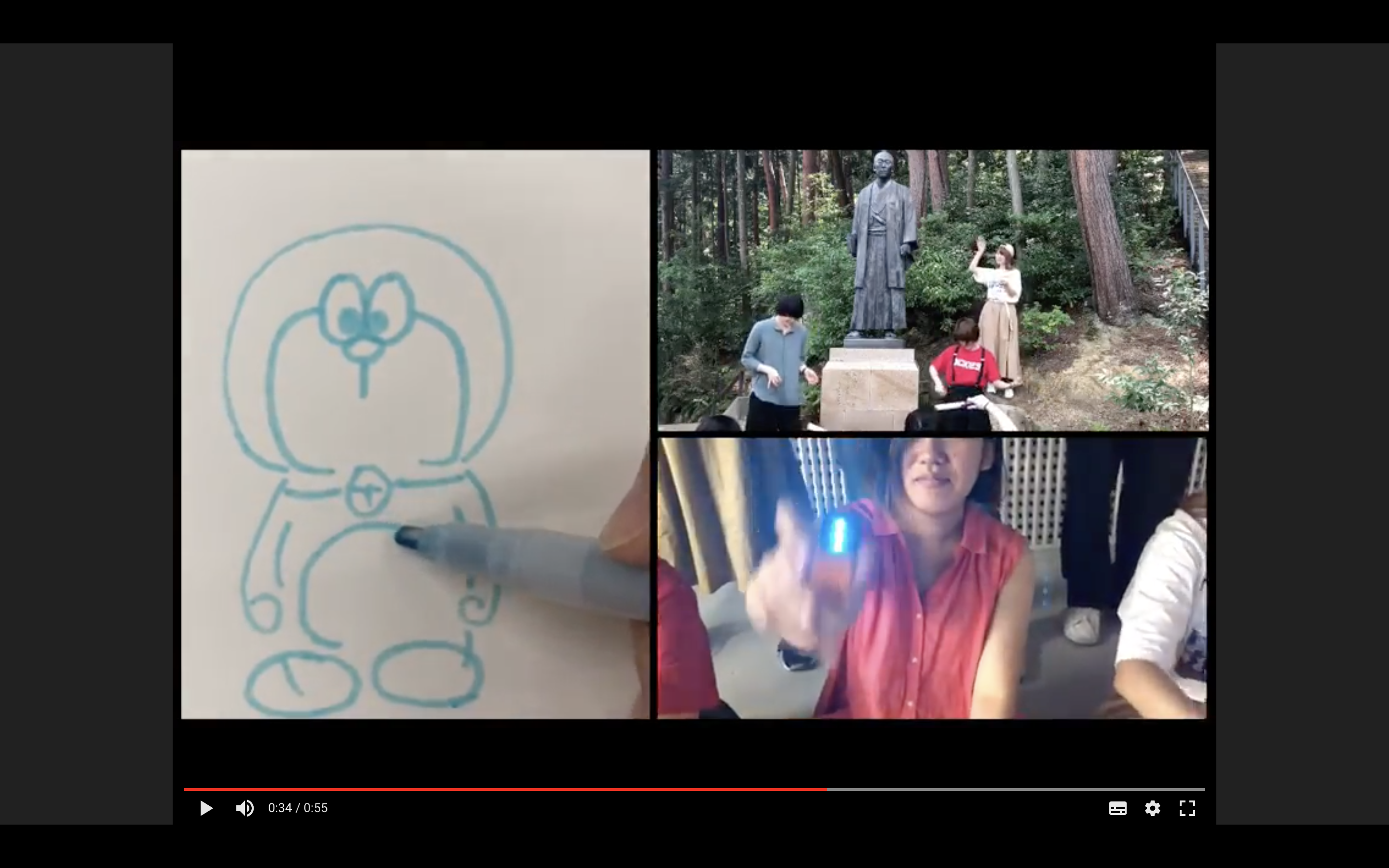MESH
2018/07/12
MESHの新しい使い方を考えた。
授業1日目 / マインドマップの作成。
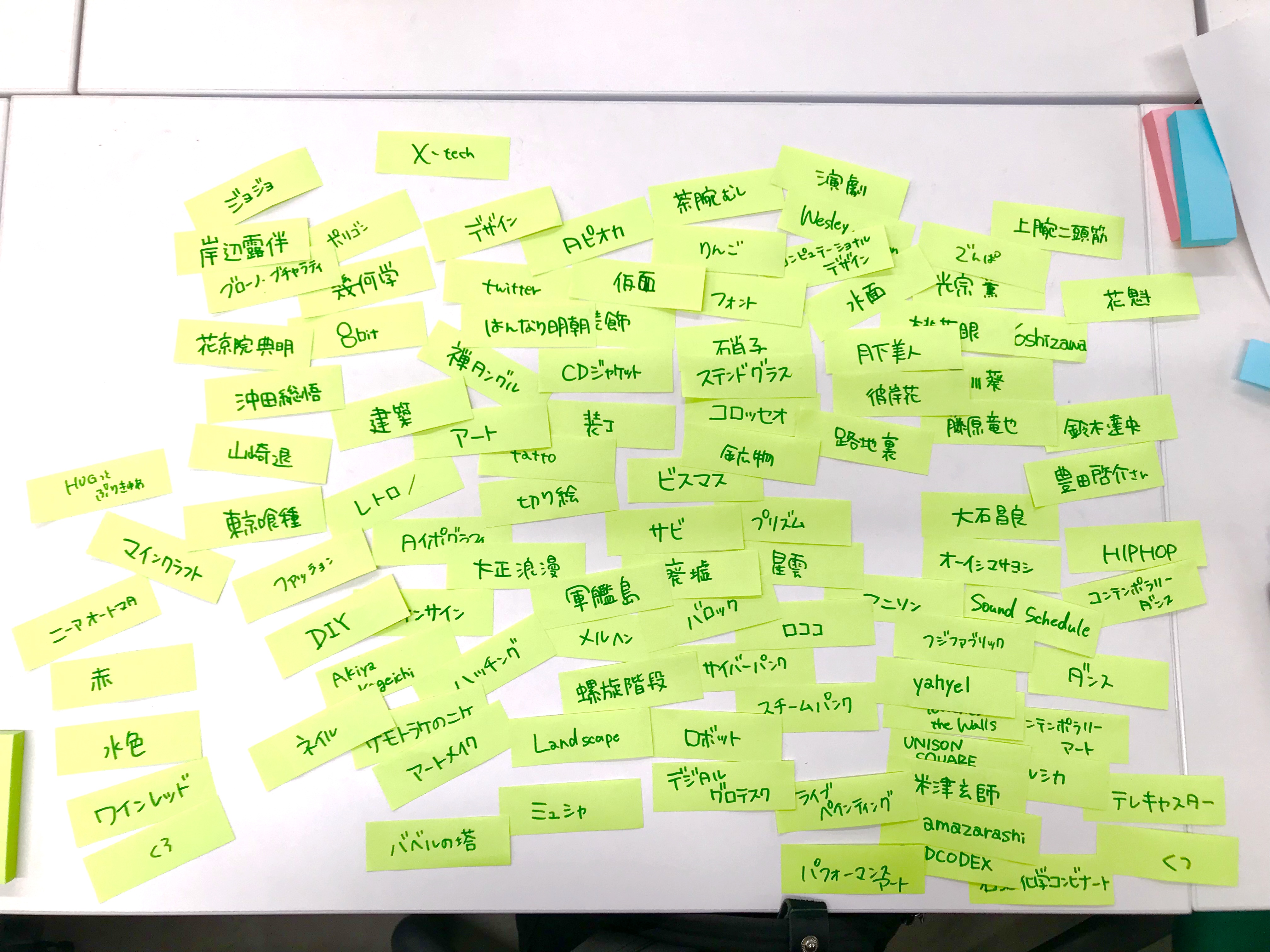
まずは好きなものをとにかくどんどん出して
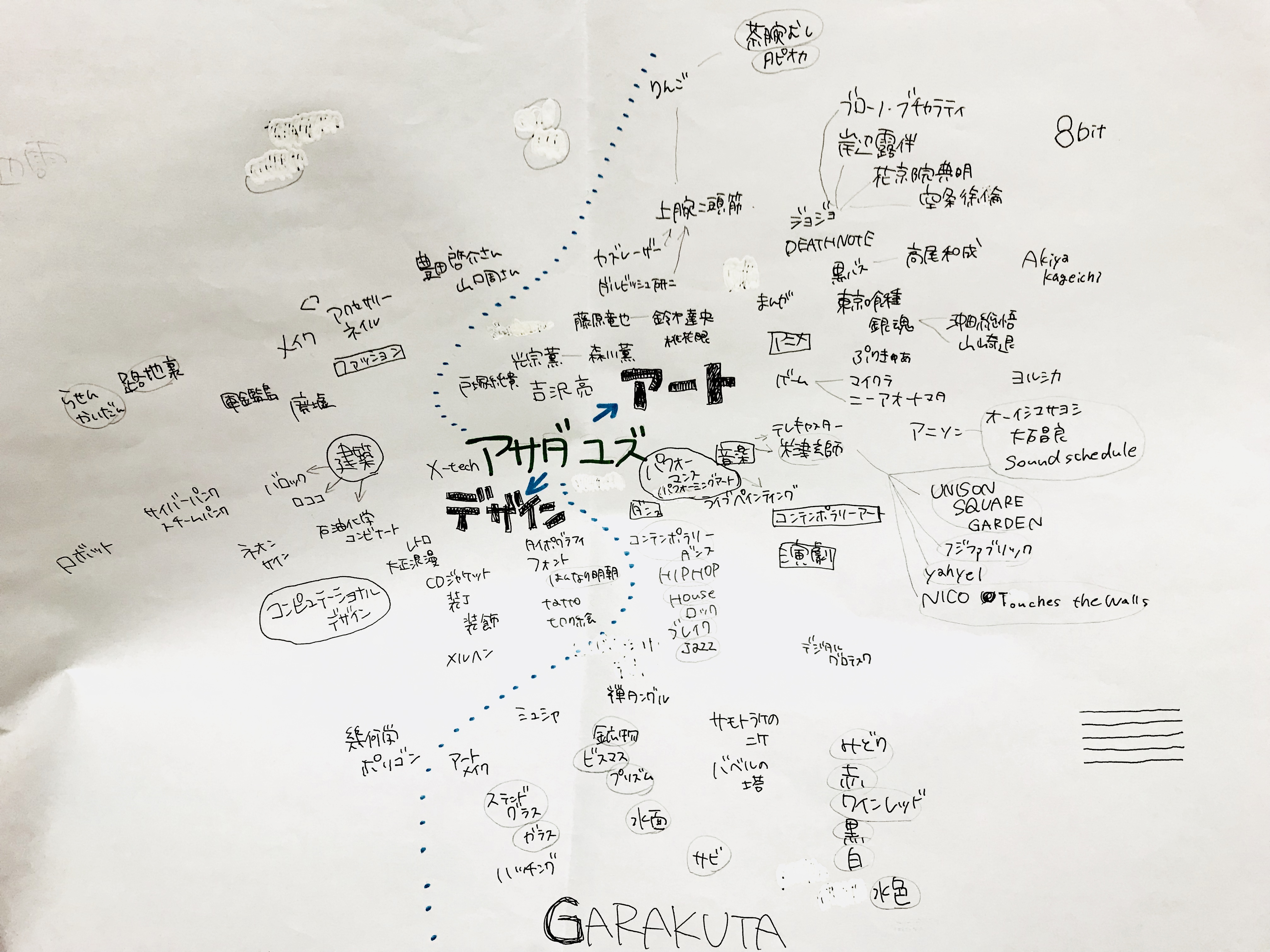
ジャンルごとに整理しつつマインドマップにまとめた。
好きなもののジャンルが広く、
具体的なものと抽象的なものが混在していたため、
この作業が一番大変だった。
授業2日目 / MESHを触ってみる
マインドマップを元に振り分けられたグループで
MESHを実際に触って、何ができそうか色々試してみた。

「身体・ストリートカルチャー」グループでは MESHを用いた
①植物とコミュニケーションをとるシステム
(入力:人感 / 出力:音声・撮影)
②階段を登る人を応援するシステム
(入力:人感 / 出力:音声)
③痴漢の撃退方法
(入力:人感 / 出力:音声)
④音楽とペインティングパフォーマンス
(入力:振動・明るさ / 出力:音声)
を考えた。
▶︎検証結果
①植物とコミュニケーションを取るシステム
植物に近づく人を感知したら、声が聞こえたり、撮影される。
入力の感度が高いという問題点はあるものの、出力は成功。
システムをより深めていけそうだという結果に。
②階段を登る人を応援するシステム
階段を登っている人を感知したら、応援ソングが流れる。
・感度が高すぎる
・大勢が階段を登る場合一人一人に応援ソングが届かない
・降りる人や立ち止まる人も応援してしまう
という問題点により、断念。
③痴漢の撃退方法
痴漢しようとする動きを感知したら「痴漢されました」という音声が流れる。
・感度が高すぎる
・痴漢をする動きとそうでない動きの違いをどう区別するか
・痴漢の防止にはなるかもしれないが問題の解決にはならない
という問題点により、断念。
④音楽とペインティングパフォーマンス
絵の具の付着を感知、筆の動きを感知したら音がなる。
出力の精度は低いが、やりたいことができた。
これも、システムをより深めていけそうだという結果に。
以上から、①と④のアイデアを発展させていくことになった。
授業3日目 / アイデアを深める
私たちは、①のグループ、④のグループに別れ、
それぞれのアイデアをより深めていった。
私が入った④のグループでは、まず出力の精度が低いという問題を解決するため、
複雑な構造を改善した。
④のアイデアの目的は「MESHを用いて表現活動を行うこと」
表現したいことをより表現しやすくするために
1つの入力で複数の出力を行うという構造から
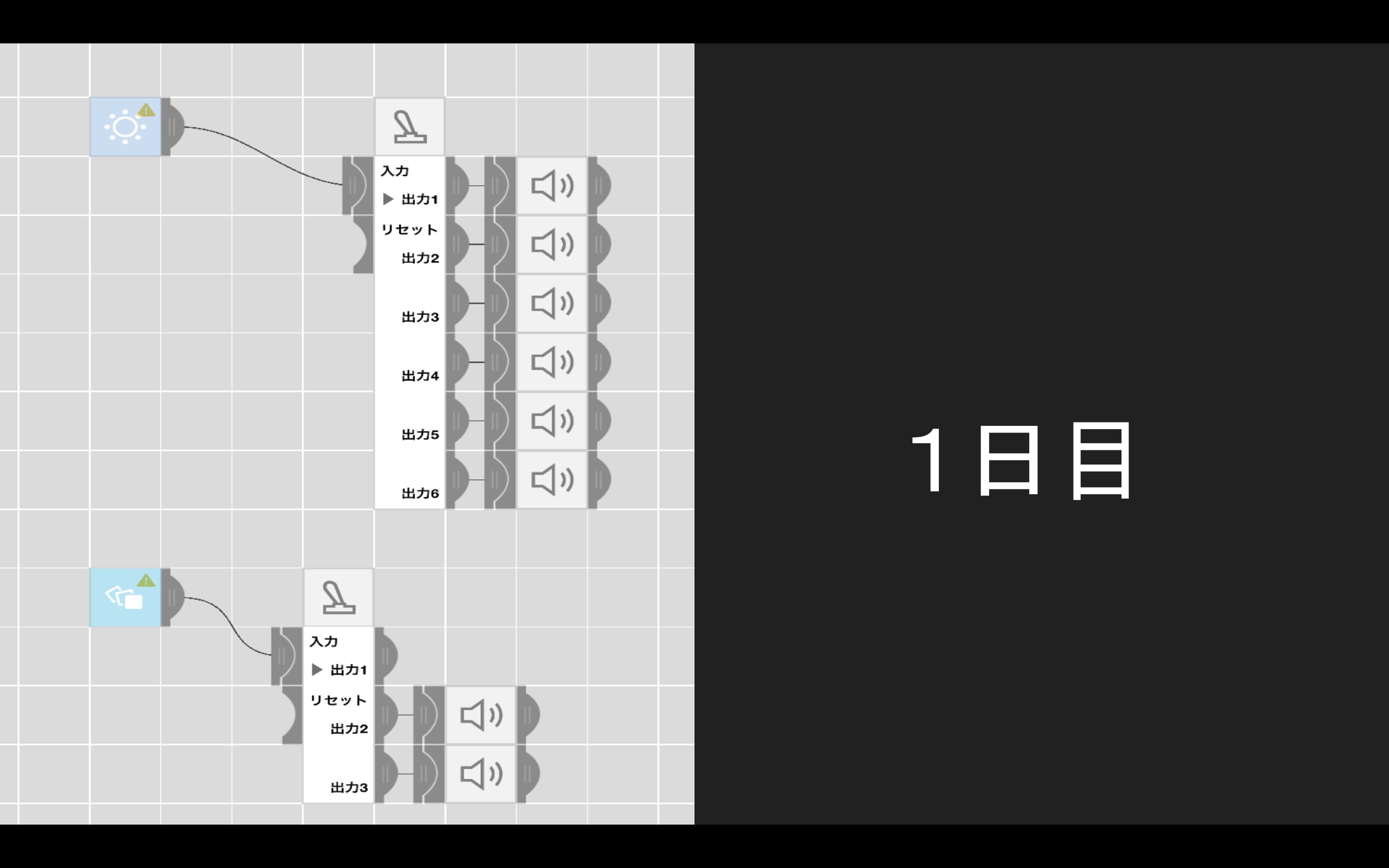
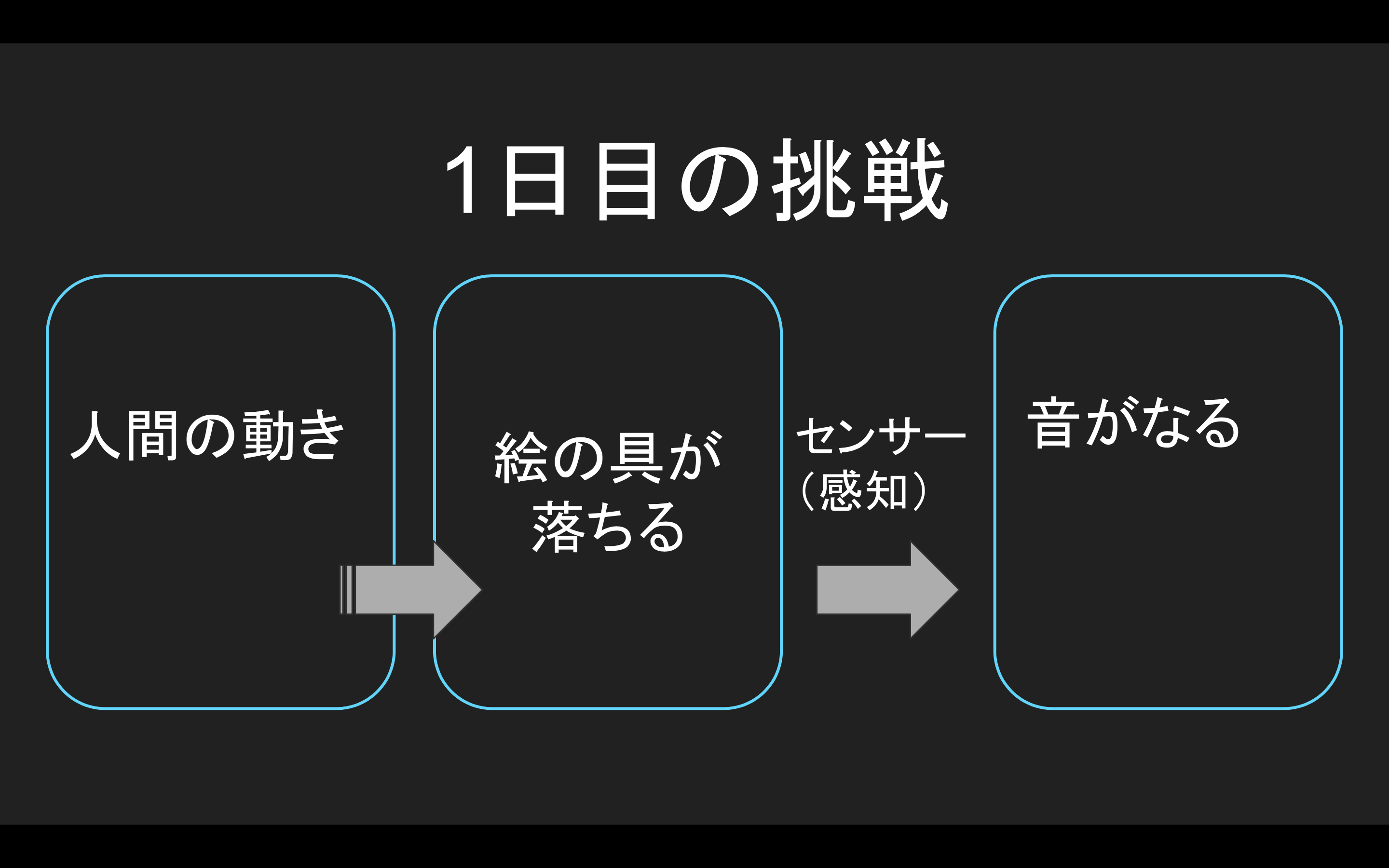
1つの入力で1つの出力、という一方通行の構造に変更。
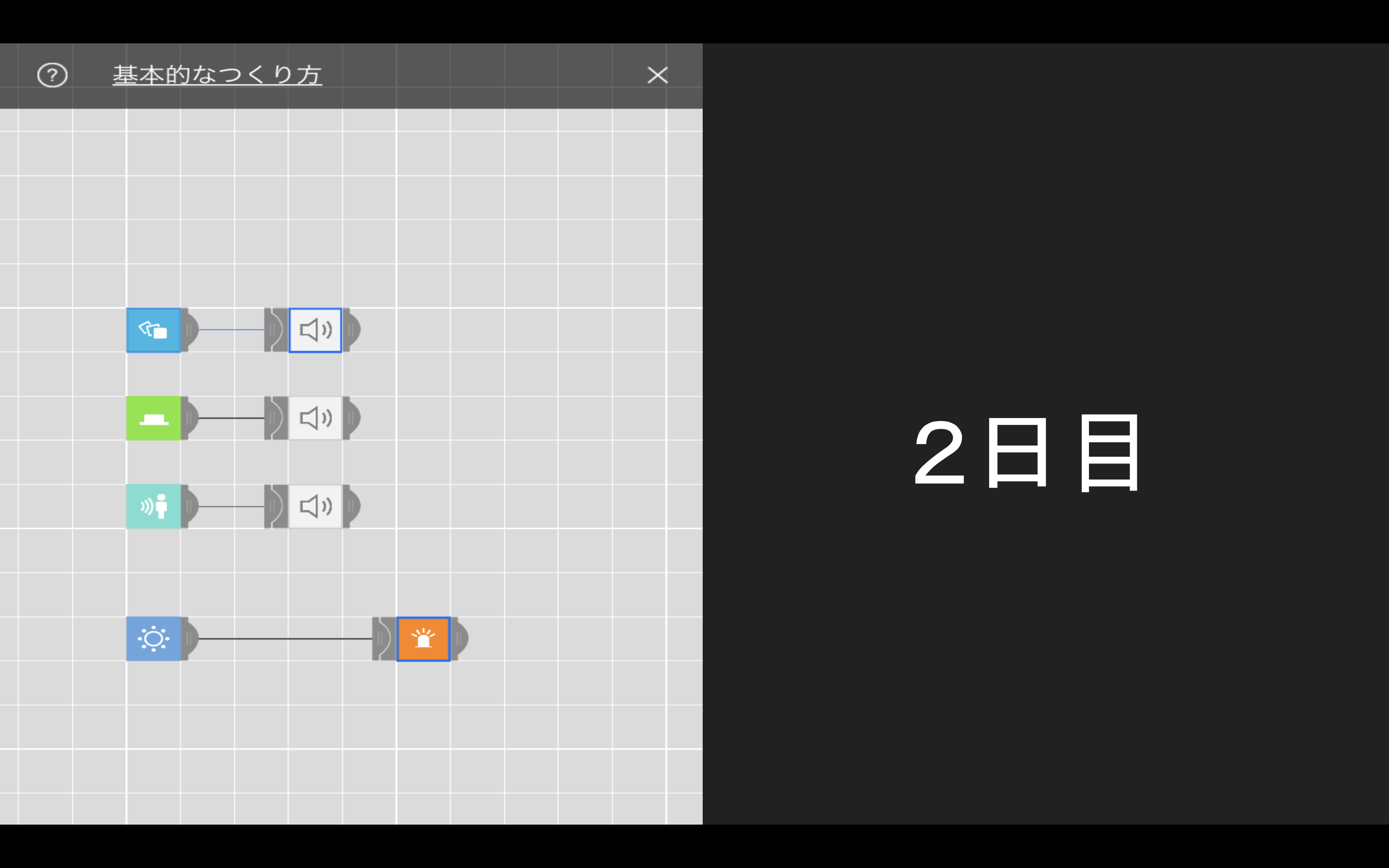

入力のバリエーションを増やすことで、複数人での入力が可能になった。
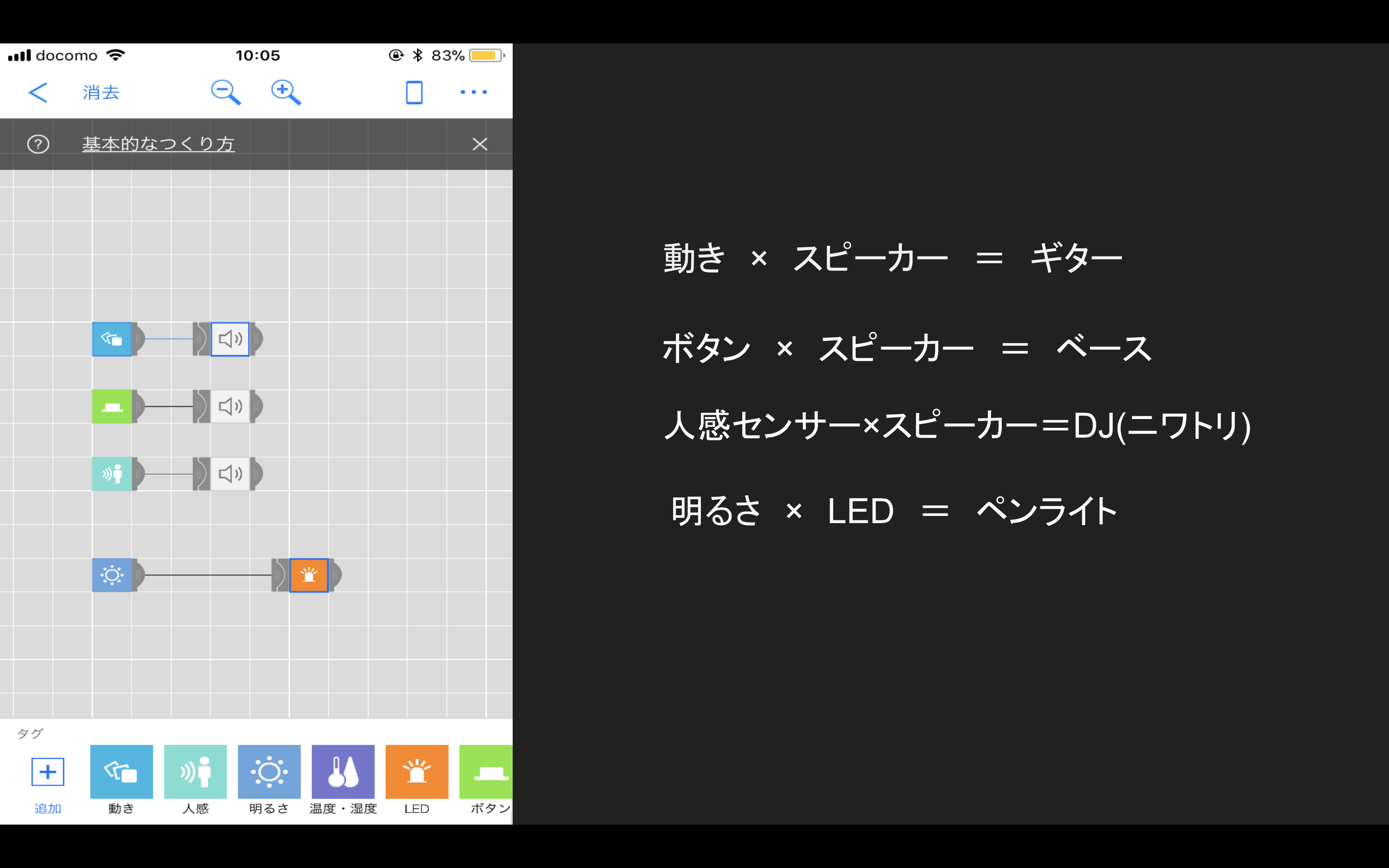
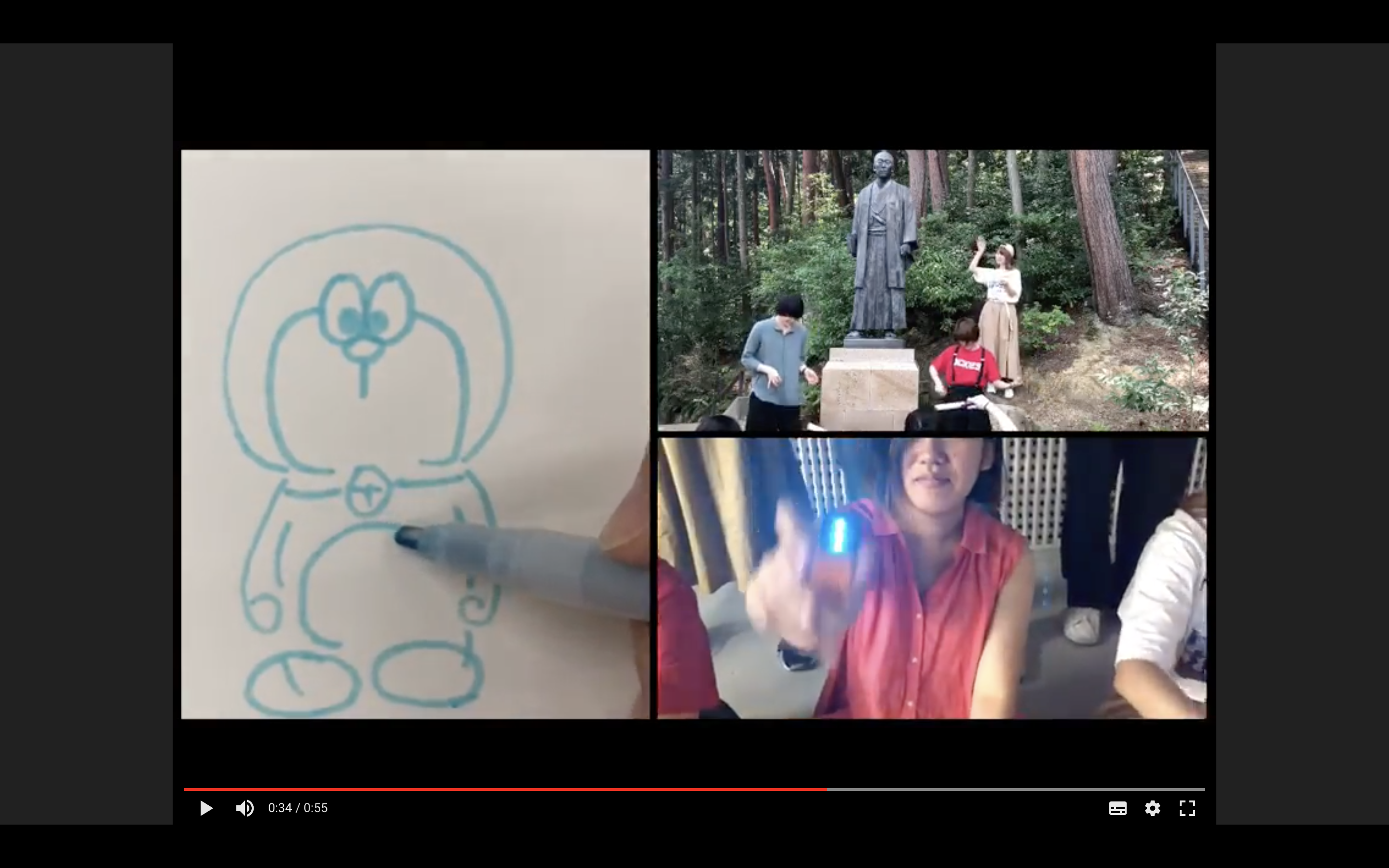
▶︎検証結果
・反応に時間差が出るが、入力→出力が前日よりもスムーズになった
・楽器を買わなくてもMESHを使って音楽を楽しめる
・場所を問わずに表現活動を行うことができる
3日間の授業のまとめ
MESHで表現の幅を広げるということに、まだまだ可能性があると感じた。
今回は「音楽」というジャンルに限定されてしまったが、
入力、出力のバリエーションを増やすと、より様々なジャンルの表現が可能になり、
そこに面白さを感じた。